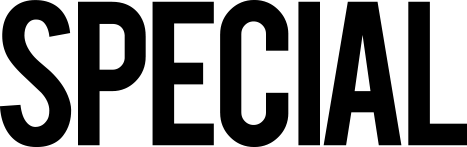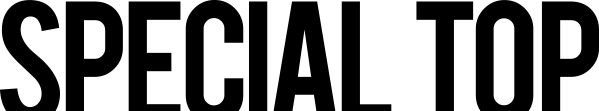ドレスコーズ「少年セゾン」志磨遼平コラム

うだるような、まるで火葬のような、夏がきた。
日なかをさまようだけで命をおとしかねない暑さ。都内では40℃を超えているところもあるという。こんなにも夏があぶなっかしくなったのは、いったいいつからだろう。
それでもきっと、8月に入れば暑さのさかりも過ぎて、ああ、もう夏も終わりじゃないか、なんてセンチメンタルになったりするんだろう。毎年のことだ。
梅雨明けからの7月いっぱい。「本当の夏」はたったの1〜2週間で、この前後に「夏のことを考えている期間」がつく。
来る夏に思いをはせ、過ぎゆく夏を惜しむための、夏の余白。夏のノンブル。
それらをひっくるめて2〜3ヶ月の期間を我々は「夏」と呼んでいる気がする。暑いのが夏なのではなく、夏のことを考えている期間こそ夏なのだ、という気がする。
と、まあ花鳥風月ではないがこうした季節のうつろいに趣(おもむき)を感じるようになったら人はおしまいだ。もう立派な晩年だ。
少年の頃はたとえ花が咲こうが鳥が鳴こうが風が吹いて月が出ようが宮崎駿が君たちはどう生きるか問うてこようが知ったこっちゃなかった。
自分にわかるのは、自分は醜い、というただそのことだけであった。
何時間も鏡の前で身繕いをし、学校では異性をねめつけ、夜になれば将来を案じて震えが止まらなくなる。そんな己の卑小さがずっと醜くて、醜くて、たまらなかった。
小遣いはすべて洋服に費やした。せめて見た目を繕わねば、外にすら出られなかった。
ナイキ、リーバイス、ノースウェーブにバケットハット。なにを着るべきか、それだけが問題だった。
級友との話題といえば《第二次性徴とそれに起因する怪談》ばかりだった。
誰かが妊娠しただとか、勃起したペニスは行為中に折れることがあるだとか、チツケイレンが起きるとそのまま救急車を呼ぶはめになるだとか。
そんな話を、ひとり夜に思い出してはまた震えが止まらなくなるのだった。まちがった大人になることが恐かった。そんな大人にすらなれる気がしなかった。我々は皆、思春期にだけ見える亡霊に取り憑かれ、おびえていた。
日曜日になれば少しだけ気が晴れた。教師や級友たちと顔を合わせずにすむからだ。
午前中のうちに家を出る。夏のウォークマンからビーチ・ボーイズの “kokomo” あたりが流れてくれれば完璧で、はやる気持ちをこらえて古着屋へとペダルを漕ぐ。風車ナイキのTシャツがじっとりと汗ばむ。
それでもまだこのころの夏の朝には、今よりも涼しい風が吹いていた。
少年セゾン、なぜかこんなことまで思い出してしまう。夏の余白。夏のノンブル。
志磨遼平